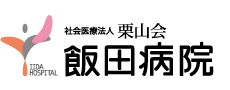放射線科
放射線科では現在技師11名、助手1名でさまざまな機器を用いて、診断に必要とされる部位の撮影を行っています。
(1)一般撮影(FPD装置)
主に骨や検診時の胸部撮影をするものです。昔は1枚1枚フィルムに撮影して暗室で現像していましたが、今はデジタル社会!皆さんもデジカメを使うようにX線写真もデジタルになっています。デジタルで画像処理ができるので撮影時のX線量もグッと少なくなりました。一般撮影室は2部屋で撮影を行っております。

(2)CT装置(320列マルチスライスCT)
X線を用いて体内の輪切りが撮れる装置です。0.5mm間隔でのスライスができるので小さな病変も写し出すことができます。2017年9月にCT装置の入れ替えを行い、被ばく線量を低減しながら160mmを1回転0.275secで撮影可能になり、撮影時間も短縮されました。また撮影後の画像を処理することにより輪切りだけでなくいろんな角度から画像を見ることができます。CTで透視をしながら生検を行ったり、造影剤を使い心臓の血管を写し出す心臓CT、他にも骨折部位なども3Dで写し出すことができます。
(3)MRI装置(1.5T MRI)
CTとは違いX線を用いないで体内を撮影することができます。造影剤を使用することなく脳内血管や下肢の血管も見ることができます。しかし装置はとても強い磁力をもった大きな磁石なため、ペースメーカーなど体内に金属の入っている方は検査ができないことがあります。

(4)SPECT装置(シンチカメラ)
放射性医薬品を用いて体内の病気を発見する装置です。脳・心臓・骨などの画像情報から治療方針の決定などに役立てています。2023年9月に装置の入れ替えとなりました。当院には認知症疾患センターがあり、この装置を用いて検査する事により認知症、アルツハイマーの早期発見に役立っています。

(5)乳房撮影装置(マンモグラフィ)
2020年2月に装置の入れ替えとなりました。現在日本の死因のトップはガンです、乳癌も年々増加傾向にあります。1年に1回はマンモグラフィ検診を受け早期発見に努めましょう。また当院ではマンモグラフィ撮影認定診療放射線技師が撮影を行っています。気になる症状がある方は外科外来へ受診してください。

(6)X線TV装置
バリウムを飲んで胃の検査を行ったりする透視装置です。他にも内視鏡を使った検査でも使われます。2013年4月に装置の入れ替えが行われデジタルTV装置に変わりました。新装置はデジタル断層撮影(トモシンセシス)も可能な装置を導入しました。整形外科で膝や股関節の手術をした後の人工関節の様子もよくわかります。

(7)骨密度測定装置(DEXA)
骨の密度を測り強度を調べる装置です。2019年8月に装置の入れ替えとなり、新たに骨質の測定も行えるようになりました。当院の健康診断では腰椎の3椎体(基本は第2腰椎から第4腰椎)を測定し骨密度を測ります。特に女性は出産時、閉経後急激に骨量が減り始め骨粗しょう症になりやすいので年1回の測定をお勧めします。

(8)ポータブル撮影装置
ベッドから動くことのできない患者さんに対してベッドサイドまで出張し撮影するコンパクトな装置です。2015年6月に挿入したFPD(フラットパネルディテクター)装置を使用しています。撮影したその場で画像を確認する事ができ、被ばく低減にも努めています。

(9)血管撮影装置(アンギオグラフィ)
造影剤を流して撮影した画像から、造影剤を流す前の画像を引き算することにより血管だけを鮮明に映し出します。心臓や透析のシャント部分の血管を撮影し狭窄しているところを膨らませて治療します。他にもペースメーカー挿入時や電池の交換の時にも使います。血管の治療など清潔での検査になりますので装置は手術室にあります。

(10)外科用・手術室用X線診断装置(外科用イメージ)
骨折の際に骨がずれてしまった場合、金属などで固定する手術が必要となります。その時、医師が骨折部位を見ながら整復するための透視装置です。
どの手術室でも移動して使用できるコンパクトな透視機能を備えた可搬形X線装置です。

そして、上記の装置から得られる画像を院内設置のモニターで必要なときに観覧できるPACS(画像保存通信システム)、KADA(動画閲覧システム)も導入してます。
以上、放射線科では常に患者さんに対して「おもいやり」をモットーに検査をしています。
| 専門・認定資格名称 | 取得者数 |
|---|---|
| X線CT認定技師 | 2名 |
| 検診マンモグラフィ撮影認定診療放射線技師 | 2名 |
| 第一種衛生管理者 | 2名 |
| X線作業主任者 | 1名 |
| PET認定技師(PET研修セミナー修了) | 1名 |
| ICLS | 1名 |
| Ai認定診療放射線技師 | 1名 |
| アドバンス診療放射線技師 | 1名 |
| シニア診療放射線技師 | 1名 |
| 赤十字救急法救急員 | 1名 |